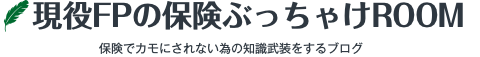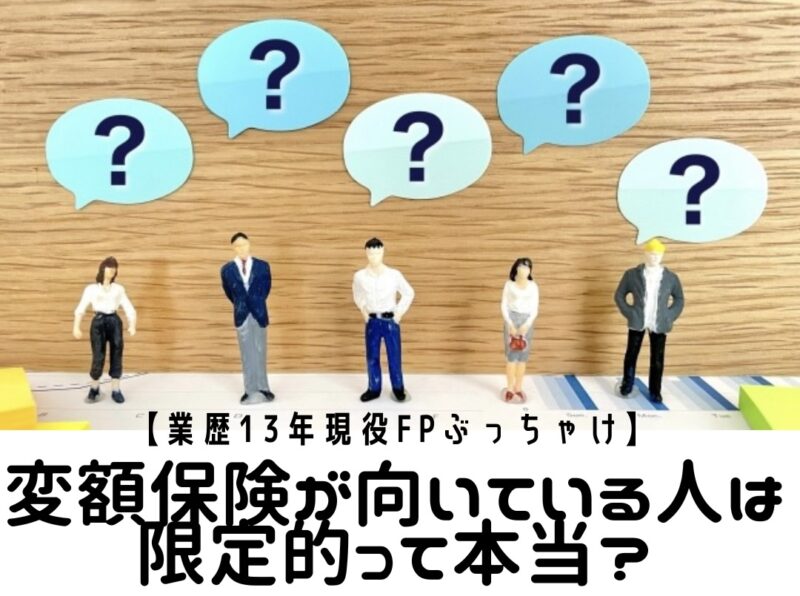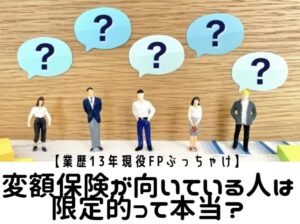色々な保険や投資方法がある中で、変額保険が最適なのかと悩む人は多いです。
当たり前ですが、全ての人に適している訳はなく、個人の考え方や様々な状況により向き・不向きがあります。
そこでこの記事では、業歴13年現役FPとして2,000世帯以上の相談を受けてきた筆者が完全中立な立場で、変額保険に向いている人の考え方、入る前の注意点を徹底解説します。
最後まで読めば、あなたが変額保険に向いているのかどうかがわかります。
\業歴13年FPがオススメする相談窓口! 悩んでいる時間が勿体無い!/
\無理な勧誘なし!オンライン相談は全国対応/
公式サイト:https://hokench.com
変額保険とは

- 変額保険の仕組み
- 変額保険は3種類
変額保険の仕組み
死亡保障に備えながら、保険料を投資信託で運用していく保険です。
投資信託の運用成果が良ければ死亡保険金・解約返戻金・満期保険金が増えるけど、運用成果が悪かったら解約返戻金・満期保険金は減ってしまい大きく元本割れを起こす可能性があります。
| 死亡保険金 | 解約返戻金 | 満期保険金 | |
|---|---|---|---|
| 最低保証の有無 | あり | なし | なし |
| 運用成果がプラスの場合 | 増加 | 増加 | 増加 |
| 運用成果がマイナスの場合 | 変化なし | 減少 | 減少 |
変額保険は3種類
- 【変額終身】:死亡保障・運用期間が一生涯
- 【変額有期】:死亡保障は期間限定、満期時に運用成果に応じた満期保険金を受取る
- 【変額個人年金】:死亡保障はなし、保険料払込終了後に運用成果に応じた年金を受取る
途中での種類変更は原則できません。
入る前に3種類全ての見積書を作成してもらい、比較してから自分に合った変額保険を選ぶようにしてください。
ちなみに、保険屋は販売手数料が一番高い【変額有期保険】を提案してくるケースが多いです。
【デメリット】変額保険でないといけない理由が何一つない
変額保険は保険会社に中抜きされる手数料が高かったり、その影響で運用効率が非常に悪かったり、死亡保障は掛捨てで備えた方が結局コスパが良かったりと、最初に知らないとあとで後悔する様々なデメリットがあります。
現役FPから客観的にみて、保障面・運用面ともに変額保険でないといけない決定的な理由が何一つなく、もっと視野を広げて考えた方が変額保険よりも良い備えができます。
変額保険はやめたほうが良い理由やデメリットについては別記事で詳しく解説してます。
3つのメリット

- 【メリット①】運用実績が良ければ積立金が増える
- 【メリット②】基本保険金額に最低保証がある
- 【メリット③】生命保険料控除が使える
【メリット①】運用実績が良ければ積立金が増える

選んだファンドの運用が良ければ、ドル建て保険や円建て保険よりも返戻率が高くなる可能性があります。
長期継続するほど、積立金が増える確率は上がることを理解しておきましょう。
【メリット②】基本保険金額に最低保証がある
死亡保険金額は保証されているので、運用実績が悪くても死亡保険金が減額されてしまうことはありません。
もし、変額保険に入って間もなく死亡してしまった場合でも、死亡保険金をしっかり遺族にのこすことが出来ます。
【メリット③】生命保険料控除が使える

生命保険料控除が使えるので、所得税・住民税の節税ができます。
いくら控除できるかは、ユニットリンク以外の加入中保険も含めた、生命保険に対しての年間支払い保険料によります。
《所得税控除》
| 年間払込保険料 | 控除される金額 |
|---|---|
| 20,000円以下 | 払込保険料全額 |
| 20,000円以上〜40,000円以下 | (払込保険料×1/2)+10,000円 |
| 40,000円以上〜80,000円以下 | (払込保険料×1/4)+20,000円 |
| 80,000円以上 | 一律40,000円 |
《住民税控除》
| 年間払込保険料 | 控除される金額 |
|---|---|
| 12,000円以下 | 払込保険料全額 |
| 12,000円以上〜32,000円以下 | (払込保険料×1/2)+6,000円 |
| 32,000円以上〜56,000円以下 | (払込保険料×1/4)+14,000円 |
| 56,000円以上 | 一律28,000円 |
ただし、変額保険以外に保険に入っていたらそれも合算しての控除となります。
\業歴13年FPがオススメする相談窓口! 悩んでいる時間が勿体無い!/
\無理な勧誘なし!オンライン相談は全国対応/
公式サイト:https://hokench.com
変額保険が向いている人

- 手軽に投資を始めたい
- 自分で投資することを諦めた
- NISA・iDeCoを満額使っている
- 相続税対策をしたい
手軽に投資を始めたい

- 「とにかく手軽に投資を始めたい」
- 「色々自分で調べるのは面倒」
- 「銀行より増える可能性があれば何でも良い」
- 「運用効率は一切重要視しない」
投資を始めたいけど重い腰がなかなか上がらないなら、保険に入れてしまえば難しいことなく投資がスタートできる変額保険が向いています。
自分で投資することを諦めた
自分で投資をしようと思ったけど、どのように始めたら良いかわからず、結局始められないままという人もいます。
そのまま諦めて投資をしないくらいなら、変額保険に入ることをオススメします。
NISA・iDeCoほど恵まれた制度ではないですが、変額保険も長期的に見れば積立金を増やせる可能性が高いからです。
NISA・iDeCoを満額使っている
NISAとiDeCoをすでに満額まで使っているなら、その次の選択肢として変額保険はありです。
でも、NISAは2024年1月から『新NISA』に生まれ変わり、上限額が年間360万(月換算30万)になります。
今現在、NISA・iDeCoを満額使っていても余力があるなら、無理に変額保険に入らず『新NISA』開始まで待つ方が良いです。
新NISAを詳しく知りたい人は別記事で解説しています。
相続税対策をしたい

死亡保険金は相続税非課税枠を基礎控除に加えて使えるので、相続税対策にも有効です。
(例)500万円 × 3人(妻・子2人)= 1,500万円が生命保険の相続税非課税限枠となる。
生命保険の相続非課税枠は、
に加えて使うことが出来ますので、相続税対策に有効です。
\業歴13年FPがオススメする相談窓口! 悩んでいる時間が勿体無い!/
\無理な勧誘なし!オンライン相談は全国対応/
公式サイト:https://hokench.com
変額保険に入る前のポイント

- 長期継続前提で入ること
- FPに家計状況と資産状況も含めて提案してもらうこと
- 変額終身・有期・個人年金の商品比較を必ずすること
長期継続前提で入ること
変額保険は短期間で積立金が増えることはありません。
最低でも15年、できれば20年以上の時間をかけて変額保険を育てていけば、元本割れリスクを抑えることができ、リターンも安定してくるので、長期継続前提で入ることを心がけましょう。
FPに家計状況と資産状況も含めて提案してもらうこと
変額保険が本当に最適なのかは、あなたの家計状況と資産状況によります。
例えば、下記の人物がいた場合、同じ投資方法を取るべきでしょうか?
- Aさん:独身20歳毎月2万円貯金可能現時点の貯金総額50万円
- Bさん:独身40歳毎月5万円貯金可能現時点の貯金総額2,000万円
貯金がなく若いAさんは、まだ貯金があまりできていないので貯金を優先して貯めてから投資を始めるか、投資するとしても少額投資としてスタートをした方が良いとアドバイスされるかもしれません。
一方、貯金が2,000万円ある40歳のBさんは、投資を優先して行うことや、貯金を活かした一括投資も選択肢に入るかもしれません。
どのマネープランが正解というものはありませんが、家計状況と資産状況や考え方によって、今何を優先すべきか変わるので、お金の専門知識豊富なFPに相談して一緒に最適なプランを考えてもらい、最適解を見つけましょう。
変額終身保険・変額有期保険・変額個人年金の商品比較を必ずすること

3種類の変額保険は死亡保障の有無に関係なく、見積書で必ず比較してもらいましょう。
何故なら、変額個人年金は死亡保障がない代わりに、運用効率が良い商品です。
その利点を活かし『変額個人年金』と『掛捨て死亡保険』を組み合わせた方が、死亡保障付きの変額終身保険・変額有期保険を上回る備えができる可能性が高いからです。
どの種類の変額保険を選んでも、外国株式のインデックスファンドで投資をする場合の差はほとんどありませんので、しっかり比較して最適なものを選びましょう。
デメリットを理解した上で変額保険に加入したい
- 保険営業の説明だけでは理解しきれなかった
- 変額保険の提案を受けたけど、難しくてよくわからなかった
- お金が増えると良い話すぎて不信感を感じて自分で調べようと思った
- NISAよりライフインベストの方が良いと言われて担当者に疑問を持った
このブログを読んでいる人は、このように感じている人が多いと思います。
変額保険は非常に複雑な保険で、メリット・デメリットや自分に適不適かしっかり理解した上で入らないと、あとで後悔する可能性が高いです。
読者の方には、そうなって欲しくありません。
- 担当の保険営業の案内に疑問をもった
- 変額個人年金の案内がなく、変額有期保険の説明しか受けていない
- NISA・iDeCoと詳しく比較してから決めたい
- 保険に固執せず幅広い金融商品の中から最適な積立方法を知りたい
このように思うなら、リクルート運営の保険チャンネルで資産形成に特化したFPに相談がオススメです。
無料FP相談サービス保険チャンネルはリクルートの厳しい審査基準をクリアし、相談内容にマッチしたFPにスマホやタブレットで全国どこでもオンライン相談ができます。
特定の金融機関に属さない資産形成に精通したFPに無料相談できるので、最適な資産形成はなにか、変額保険・NISA・iDeCoなど保険以外の金融商品と詳しく比較しながら、あなたに最適なマネープランが見つかります。
金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度など、避けては通れないお金の悩みをなんでも相談できるのがメリットです。
スマホやタブレットから全国どこでもオンライン相談ができて、押し売りは一切なしとホームページで公言しており、ノーリスクで相談できるので安心です。
リクルート運営の保険チャンネルで、まずは気軽に無料相談してみましょう。
\業歴13年FPがオススメする相談窓口! 悩んでいる時間が勿体無い!/
\無理な勧誘なし!オンライン相談は全国対応/
公式サイト:https://hokench.com
まとめ
- 変額保険がオススメな人は限定的
- 「手軽に投資を始めたい」「自分で投資するのを諦めた」「NISA・iDeCoを満額使っている」「相続税対策をしたい」
- このような人には変額保険が向いています。
- もし変額保険に入るなら「変額終身」「変額有期」「変額個人年金」は必ず比較しよう
- 保険・投資のことならリクルートが厳選した資産形成に特化したFPに相談がオススメ。
\業歴13年FPがオススメする相談窓口! 悩んでいる時間が勿体無い!/
\無理な勧誘なし!オンライン相談は全国対応/
公式サイト:https://hokench.com